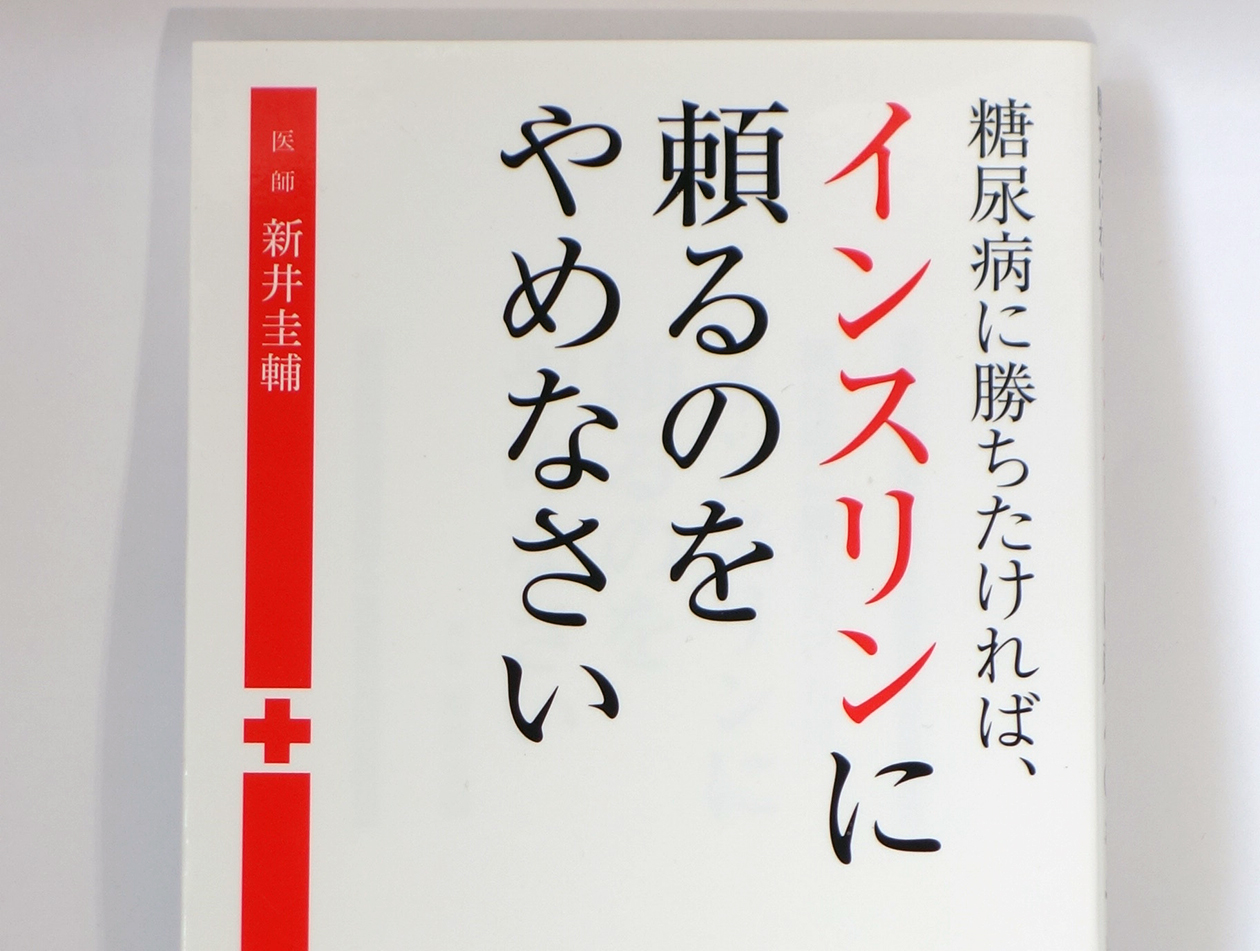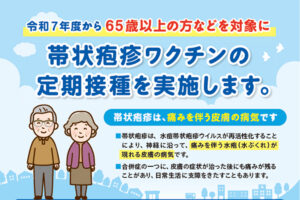インスリンの重要性
「肥満ホルモン」とも呼ばれる「インスリン」。
「フェロモンなら大歓迎だけど、このホルモンはちょっと…」と思うのは、私だけでしょうか?
インスリンは、私たちの体にとって必要不可欠なホルモンです。
もしインスリンが分泌されない体になってしまうと、自分で注射しなければなりません。
糖尿病(1型)の方が、お腹に注射しているのがインスリンです。
ちなみに、インスリンは口から摂取すると分解されてしまうため、現在のところ(2025年3月時点)注射による投与しか方法がありません。
このように体にとって非常に重要なホルモンであるインスリンですが、体内に過剰に存在すると、様々な問題を引き起こす可能性があります。
では、なぜインスリンが過剰だと体に悪影響を及ぼすのでしょうか?
糖尿病合併症の進行
とはいえ、私自身は専門家ではないので、ここでは信頼できる専門家の著書をご紹介させてください。
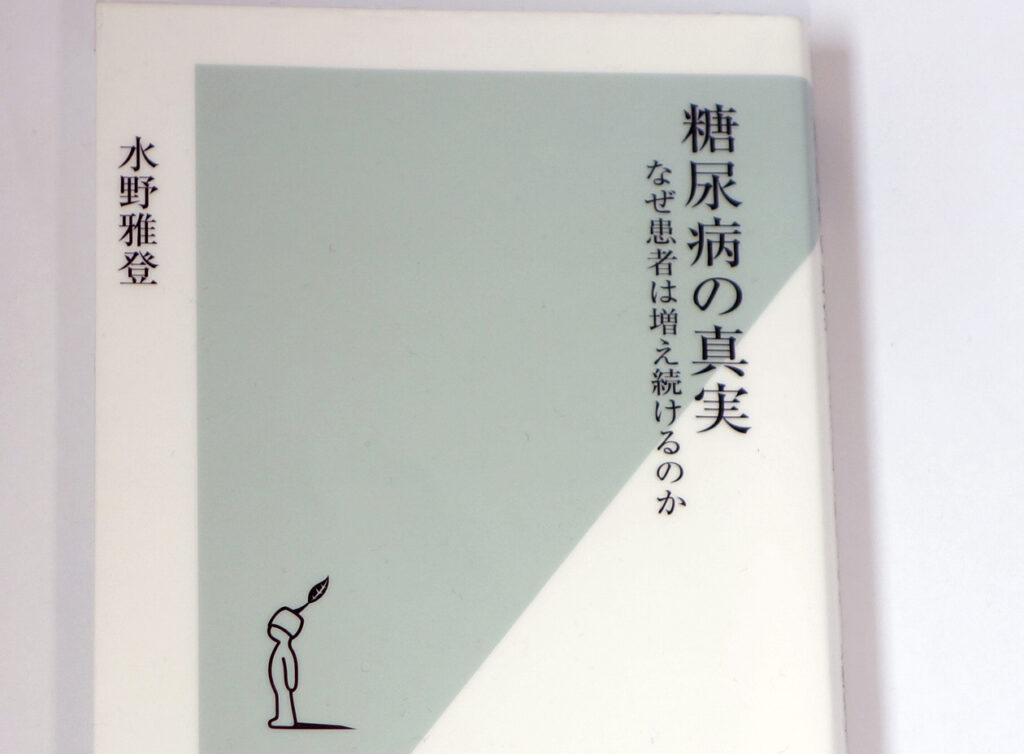
水野雅登医師の『糖尿病の真実 なぜ患者は増え続けるのか』(2021年、光文社新書)という本です。
この本の素晴らしい点は、インスリンに対する考え方が、一般的な医療の常識とは大きく異なる点です。
第2章のタイトルは、ずばり「糖尿病の真の黒幕、インスリン」。
誤解のないように補足しておきますが、ここでいう糖尿病とは2型糖尿病を指しています。
一方、1型糖尿病は、インスリンをほとんど分泌できない状態なので、本書のこのタイトルは当てはまりません。
実は、私も水野医師や新井圭輔医師の著書『糖尿病に勝ちたければ、インスリンに頼るのをやめなさい』(2016年、幻冬舎)を読むまでは、高血糖自体が体に悪いものだと信じていました。
しかし、実際には、高血糖状態でも糖尿病の合併症が進まないケースもあるそうです。
糖尿病の三大合併症といえば、「網膜症」「腎症」「神経障害」ですね。
糖尿病性網膜症が進むと、眼底出血や失明をします。糖尿病性腎症が進めば、腎不全となり人工透析が導入されます。糖尿病性神経症が進むと、手足の先から感覚が鈍くなり、怪我をしたり、糖尿病性壊疽になってもわからなくなります。(水野 2021、p.128-129)1
驚くべきことに、糖尿病の合併症が進行しなかった人たちは、インスリンが多くない状態だったというのです!
水野医師は、多くの症例から以下の2点を確認されたと述べています。
- 高血糖・低インスリンで合併症が進まない
- 血糖値が低下しても、高インスリン状態で合併症が進む
さらに、水野医師は、糖尿病の三大合併症とは別に、「インスリンの三大慢性リスク」というものも指摘しています。
それは、「肥満」「認知症」「がん」です。
これらのリスクについて詳しく知りたい方は、ぜひ水野医師の著書『糖尿病の真実 なぜ患者は増え続けるのか』を手に取ってみてください。
広く行われている糖尿病の標準治療とは
一方、現代の糖尿病治療における標準的な治療法は、新井圭輔医師や水野雅登医師の考え方とは大きく異なります。
最も大きな違いは、インスリンに対する考え方です。
標準治療では、すい臓のベータ細胞を休ませ、インスリン分泌機能を温存するために、早期からのインスリン自己注射が推奨されています。
実際、すい臓からのインスリン分泌を促す薬を服用しているにもかかわらず(自己分泌能があるにもかかわらず)、インスリン注射が必要とされて併用する患者さんもいます。
しかし、インスリン注射によって多くのインスリンが体内に入ると、前述のケースと同様に、たとえ血糖値が低下しても合併症が進行してしまう可能性があります。
医師のすすめに従い、良かれと思ってインスリン注射を続けていた人が、足の壊疽で切断を余儀なくされるような事態は、決してあってはならないことです。
低インスリン状態を保つ
インスリンによる様々なリスクを回避するために、新井圭輔医師は「低インスリン療法」、水野雅登医師は、「インスリン・オフ療法」を提唱されています。
従来の糖尿病治療では、すい臓からインスリンを分泌させる薬が主流ですが、「低インスリン療法」や「インスリン・オフ療法」では、逆にインスリンの分泌が過剰にならないことを目指します。
糖尿病でなくとも、1日に3回大量の糖質を摂取し、その度にインスリンが過剰に分泌されると、活性酸素が発生し、体は糖尿病患者と同じように「酸化ダメージ」を受けます。
この「酸化ダメージ」は、全身の血管や神経を傷つける原因となります。
そして、これが動脈硬化や血管の詰まり、神経障害へとつながっていきます。
「自分は大量の糖質を摂っていないから大丈夫」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、現代の一般的な食事には、想像以上に多くの糖質が含まれています。

食事以外でも、この世の中には、糖質があふれています。
高タンパク質、高脂質、低糖質の食事を心がけ、低インスリン状態を維持することが重要です。
インスリンがどういう時に分泌されるかは、先日の記事「疲れるのは歳のせい?」の「4|糖質をとると体で起きる変化」で書いたので、そちらも参考にしてくださいね。
参考文献
- 水野雅登(2021年)『糖尿病の真実 なぜ患者は増え続けるのか』、光文社新書 ↩︎