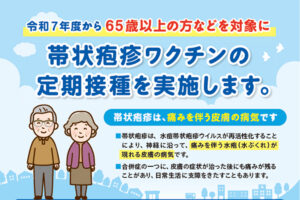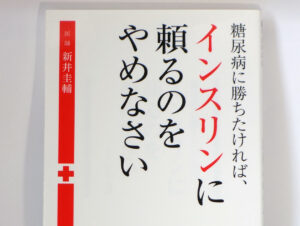親せきの高校生が遊びに来ました。
うちが糖質を控えているのを知っていたのでしょう。
いつもは甘いおやつを持ってきてくれていたのですが、今回はせんべいのサラダ味 !!
甘いものでなく、塩辛いものをチョイスしてくれたようですが...
「糖質」とは甘いものに限らない
「糖質」と聞くと、どうしても甘いものを想像してしまいますが、実はお米や小麦粉、じゃがいもでできているものも糖質なんですよね。
食パンや白ごはんだけでなく、おかきやポテトチップス、粉ものなどもそうです。
糖質制限で有名な江部康二医師は、『名医が考えた 認知症にならない最強の食事術』(宝島社、2020年)の中で「糖質」について次のように書いています。
糖質とは、たんぱく質・脂質と並ぶ「三大栄養素」の一つ。現代の食生活においても、糖質はすっかりおなじみの存在です。砂糖たっぷり使った甘いお菓子やジュースなどの清涼飲料水にはたくさんの糖質が含まれています。
しかし気をつけるべきは、甘いものだけではありません。むしろ、1日3食きちんと主食を中心に、主菜、副菜をバランスよくそろえた食事をしている方が危ないのです。なぜなら私たちが「主食」としているご飯やパン・麺類などの「炭水化物」とは、糖質をたっぷり含んでいるからです。そもそも「炭水化物」とは、「糖質 + 食物繊維」のこと。よって、認知症を予防するためには、糖質のもとになる炭水化物を控える食事法が必要になるのです。ただし炭水化物には食物繊維も含まれているので、炭水化物を減らす場合はほかの食品から食物繊維を摂ることも意識しておきましょう。
「ごはんはきちんと食べるし、間食もほとんどしない」
「甘いものはできるだけ控えている」
そう思っている方も、意外と糖質を摂りすぎている可能性があるのです。
糖質の摂りすぎの思わぬ弊害
糖質の甘くない側面をもう一つご紹介しましょう。
糖質を摂りすぎると、「糖尿病」はもちろんのこと、「認知症」や「白内障」といった病気のリスクも高まります。
これらの病気は、加齢に伴うものと思われがちで、あまり身近に感じない方もいるかもしれません。
しかし、糖質の過剰摂取は、意外なところにも影響を及ぼします。
その1つが「関節炎」です。
「関節炎」には、「糖化」という現象が関わってきます。
「糖化」とは
「糖化」とは、糖質が熱などの影響で他の物質と結合する現象のことです。
身近な例としては、パンを焼いた際に表面が茶色くなることが挙げられます。
これは、香ばしい匂いの元となるメイラード反応として知られています。
そして、この「糖化」は、私たちの体内でも起こり得るのです。
膝の痛みの原因としてよく知られる「変形性膝関節症」は、これまで、使いすぎによる軟骨の摩耗や、体重増加による関節への負担などが主な原因と考えられてきました。
ところが、問題はもっと複雑なようです。
アメリカの医師が書いた『小麦は食べるな!』という書籍には、次のような記述があります。
小麦だけでなく、糖質全般の摂取で「糖化」という現象が起こるため、以下の記述に出てくる「小麦」を「炭水化物」に置き換えて読んでみてください。
小麦による関節への攻撃は何年も続きますが、それに拍車をかけるもう一つの現象が糖化反応です。小麦食品は大半の食品より血糖値、つまり血中のブドウ糖量を増やすことを思い出してください。小麦食品を食べれば食べるほど、血糖値がより高く、より頻繁に上昇し、その結果、糖化反応も増大します。
糖化反応が起こると、膝や股関節や手などの関節を含めた血液や体組織のタンパク質にもはや戻すことのできない変化が生じます。
関節の軟骨は、とりわけ糖化の影響を受けやすいものです。軟骨細胞は寿命が非常に長い代わりに再生不能だからです。軟骨細胞はいったん損傷を受けると、回復できません。25歳のころとまったく同じ軟骨細胞があなたの膝に存在し、80歳になってもそこにあります(あるはずです)。そのため、これらの細胞は血糖値の上下などの生涯にわたる生化学的な変化すべてに影響されやすいのです。コラーゲンやアグレカンといった軟骨のタンパク質が糖化されると、異常に硬くなります。糖化による損傷は蓄積され、軟骨はもろくて曲がりにくくなり、やがてぼろぼろになります。そして、関節の炎症と痛み、破壊――まさに関節炎の特徴が生じるのです。
Dr.ウィリアム・デイビス.小麦は食べるな!.白澤卓二[訳].日本文芸社,2013
膝の痛みに顔をしかめ、足を引きずって歩いている方も、糖質の摂りすぎが関係している可能性があるのです。
今、話題のAGEs
そして、この「糖化」がさらに進んだものが「AGEs(終末糖化産物)」です。
「エージ」や「エージズ」と呼ばれることもあります。
簡単に言えば、「こげ」です。
鍋底にこびり付いた「こげ」は、なかなか落ちませんよね。

同じように、私たちの体の中に「こげつき」があれば、スムースに機能するはずがないのです。
冒頭でも出てきた江部康二医師は、AGEsについて
近年、認知症予防に関連して注目されているのが「AGEs(終末糖化産物)」です。このAGEsは「糖化」という現象によって生み出されます。糖化とは、ブドウ糖などの糖質が加熱によってたんぱく質や脂質とくっついてしまう化学反応のこと。
糖化反応は人の体内でも起こります。食事から糖質を摂取すると、消化吸収されて、血液中のブドウ糖濃度が上昇します。そのブドウ糖(血糖)が体温で温められると、体内のさまざまなたんぱく質や脂質と結合する糖化反応が起こるのです。ただ結合したからといってすぐにAGEsになるわけではありません。
たとえば、赤血球の中にヘモグロビンというたんぱく質がありますが、それに血糖がへばりついたものが「ヘモグロビンA1c(HbA1c)」です。このヘモグロビンA1cは糖化の初期の段階の物質ですが、糖尿病かどうかを判断する際のチェック項目です。血液中におけるこの数値が高くなるほど、糖尿病の疑いが濃くなるわけです。ヘモグロビンA1cは、糖化の初期の段階なので、まだ分解・代謝ができます。しかし、体内のさまざまなたんぱく質(皮膚、骨、血管など・・・・・・)にブドウ糖がへばりついて、さらに糖化が進むと分解が困難な終末糖化産物・AGEsになります。
江部康二.名医が考えた 認知症にならない最強の食事術.宝島社,2020
と、書かれています。
体の中の「糖化」を知るには
血液検査で測定する血糖値は、空腹時や食後で数値が変動します。
一方、HbA1c(エーワンシーと略されることもある)は、過去1〜2ヶ月間の平均的な血糖値を反映すると言われています。
そのため、直前の食事による影響を受けません。
ご自身の体の「糖化」の程度を知る目安として、このHbA1cの測定をお勧めします。
一般的に、HbA1cの基準値は6.0%未満とされており、これを超えると糖尿病予備軍と診断されることがあります。
HbA1cは、「糖化」の進行度合いによって緩やかに変動し、数日で大きく変化することはありません。
例えば、1ヶ月後の検査で、先月より0.1%上昇しているといった変化が見られることがあります。
血糖値が著しく高い状態では、HbA1cが10%を超える方もいらっしゃいます。
ちなみに、普段から糖質を制限している私の半年前のHbA1cは5.5%でした。
通常の健康診断では、HbA1cが検査項目に含まれていないことも少なくありません。
もし含まれていない場合は、「HbA1cも検査してください」と申し出れば、500円程度の追加料金で測定してもらえる医療機関が多いようです。